【2025年最新】コロナ特例貸付の返済猶予は延長できる?免除条件・申請方法・相談窓口を徹底解説
新型コロナウイルスの影響で収入が減った多くの世帯を支えた「生活福祉資金特例貸付(コロナ特例貸付)」。受付は2022年9月で終了しましたが、2023年から2025年にかけて、いよいよ本格的な返済(償還)期間を迎えています。 [16]
しかし、コロナ禍の影響が長引いたり、昨今の物価高騰が追い打ちとなったりして、「とても返済できる状況ではない」と不安を抱えている方も少なくないでしょう。実際、会計検査院の調査では、2024年3月末時点で貸付総額の約3割にあたる4,684億円が返済免除となっています。
この記事では、「返済が難しい…」と悩んでいる方のために、2025年時点の最新情報に基づき、コロナ特例貸付の返済猶予や免除といった救済措置について、初心者にも分かりやすく徹底解説します。申請方法や相談窓口も具体的に紹介しますので、一人で抱え込まず、利用できる制度がないか確認していきましょう。
コロナ特例貸付とは? まずは制度の基本をおさらい
本題に入る前に、まずはコロナ特例貸付がどのような制度だったか、基本を振り返っておきましょう。

コロナ特例貸付は、新型コロナの影響で収入が減少し、生活に困窮する世帯を対象とした公的な貸付制度です。主に以下の2種類がありました。
- 緊急小口資金:主に休業した方向けに、一時的な生活費として最大20万円を貸付。
- 総合支援資金:主に失業した方等向けに、生活再建までの費用として月最大20万円(原則3か月、最大9か月)を貸付。
この制度の大きな特徴は、無利子・保証人不要で借り入れができた点です。さらに、返済時に収入が回復せず一定の要件を満たす場合は、返済が免除される特例が設けられており、生活困窮者に配慮したセーフティネットとしての役割を担っていました。 [1]
【2025年最新】返済はいつから?据置期間の延長措置まとめ
当初の契約では、借入から1年後に返済が始まる予定でしたが、コロナ禍の長期化を受けて、国は返済開始を猶予する「据置期間」の延長措置を行いました。これにより、実際にいつから返済が始まるかは、借りた資金の種類によって異なります。
2025年7月現在、多くの方が返済開始済み、または開始直前の状況です。ご自身の状況を下の表で確認してみてください。
| 貸付の種類 | 据置期間終了 | 返済開始時期 |
|---|---|---|
| 緊急小口資金 | 2022年12月末 | 2023年1月~ |
| 総合支援資金(初回貸付) | 2022年12月末 | 2023年1月~ |
| 総合支援資金(延長貸付) | 2023年12月末 | 2024年1月~ |
| 総合支援資金(再貸付) | 2024年12月末 | 2025年1月~ |
※上記は国の統一的な措置であり、個別の契約状況によって異なる場合があります。
特に総合支援資金の「再貸付」まで利用した世帯は、2025年1月から返済が始まったばかりです。 [9] ご自身の返済開始時期がわからない場合は、借入を行った都道府県の社会福祉協議会(社協)に確認しましょう。
返済が難しい場合の救済措置①:返済免除(償還免除)の仕組み
「どうしても返済の目処が立たない」という場合に、まず検討したいのが返済免除(償還免除)の制度です。これは、特定の条件を満たすことで、借りたお金の返済義務がなくなる、最も強力な救済措置です。
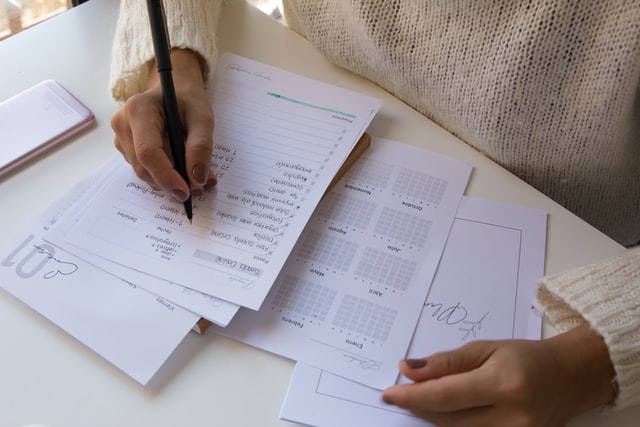
返済免除の対象となる条件
返済免除の最も重要な条件は、「借受人(借りた本人)と、その世帯の世帯主の両方が、住民税非課税であること」です。 [1, 2, 3]
この「住民税非課税」とは、前年の所得が一定の基準以下で、住民税の「所得割」と「均等割」の両方が課税されない状態を指します。基準となる所得額はお住まいの自治体や家族構成によって異なりますが、例えば東京23区内の単身者の場合、年間の合計所得金額が45万円以下(給与収入のみなら100万円以下)が目安です。
どの年度の住民税が非課税である必要があるかは、貸付の種類や申請時期によって細かく定められています。 [5, 8, 16] 該当する可能性のある世帯には、返済開始時期が近づくと、お住まいの都道府県の社会福祉協議会から「償還免除申請のご案内」という書類が郵送されます。 [2] この案内に従うことが手続きの基本となります。
【重要】住民税非課税であっても、自動的に免除にはなりません。必ずご自身で期限内に申請手続きを行う必要があります。 [5] 案内が届かない場合や、ご自身が対象か分からない場合は、必ず社協に問い合わせてください。 [1]
住民税非課税以外にも、以下のようなケースでは返済免除の対象となる場合があります。 [2, 3]
- 借受人が生活保護を受給している場合
- 借受人が死亡、または失踪宣告を受けた場合
- 借受人が自己破産や個人再生の手続きを終え、免責が確定した場合
- 精神保健福祉手帳(1級)や身体障害者手帳(1・2級)などの交付を受けている場合
返済免除の申請方法
- 社会福祉協議会からの案内を確認する:対象となる世帯には、都道府県の社協から申請書が同封された案内が郵送されます。 [2]
- 必要書類を準備する:主に以下の書類が必要です。 [5]
- 償還免除申請書(案内に同封)
- 住民票(世帯全員分、続柄記載のもの)
- 住民税の非課税証明書(借受人と世帯主の両方分)
- 期限内に郵送で提出する:書類を揃え、案内状に記載された期限までに、指定された宛先(都道府県社協の事務センターなど)へ郵送します。
申請後、審査が行われ、免除が決定すれば通知が届き、返済が不要となります。もし申請を忘れてしまうと、本来免除されるはずだった借金も返済義務が残ってしまうため、くれぐれもご注意ください。 [2]
返済が難しい場合の救済措置②:返済猶予の延長制度
「免除の条件には当てはまらないけれど、今すぐの返済は厳しい…」という方向けに、返済猶予(償還猶予)の制度があります。 [4, 15]
これは、返済の開始を原則1年間待ってもらうことができる制度です。猶予期間中は延滞扱いにならず、遅延損害金も発生しません。あくまで返済を先延ばしにする措置ですが、その間に生活を立て直す時間を作ることができます。
返済猶予の対象となる条件
返済猶予は、以下のようなやむを得ない事情で返済が著しく困難な場合に認められる可能性があります。 [4, 15]
- 失業や離職により収入が途絶えた
- 病気や療養中で働くことができない
- 自然災害で被災した
- 奨学金など、他の公的な借入で返済猶予を受けている
- 収入が不安定で、公共料金の滞納が続くなど生活が苦しい
上記はあくまで一例です。これらの事情を証明する書類(離職票、診断書など)の提出が求められます。 [15]
返済猶予の申請方法
- 市区町村の社会福祉協議会に相談する:まずはお住まいの地域の社協に電話などで連絡し、返済猶予の相談をしたい旨を伝えます。 [4, 15]
- 担当者と面談(生活相談)を行う:現在の収入や生活状況を説明し、担当者と一緒に返済計画を見直します。 [15]
- 申請書類を提出する:猶予が妥当と判断されれば、申請書が渡されます。必要事項を記入し、状況を証明する書類を添付して提出します。
【重要】返済猶予の申請は、必ず返済を滞納する前に行ってください。一度滞納してしまうと、督促が始まり、年3%程度の延滞金が発生する可能性があります。返済が厳しいと感じたら、すぐに相談することが何よりも大切です。 [18]
それでも返済できない…滞納する前に知っておきたいこと
Q. 滞納したら「ブラックリスト」に載りますか?
A. 基本的には、載りません。
コロナ特例貸付は公的な貸付であり、民間の金融機関のように信用情報機関(CICなど)に返済状況が登録されることはありません。 [20, 21] そのため、返済が少し遅れたり、猶予や免除の申請をしたりしたこと自体で、いわゆる「ブラックリスト」に載ってクレジットカードが使えなくなる、といったことはありませんのでご安心ください。
ただし、注意が必要です。何の連絡もせずに滞納を続け、社協からの督促にも応じない場合、最終的には裁判所を通じた法的手続き(訴訟や財産の差し押さえ)に移行する可能性があります。 [22] もし自己破産などの債務整理を行うことになれば、その事実は信用情報機関に登録されます。 [19] そうなる前に、必ず社協に相談しましょう。
Q. 少額でも返済を続ける方法はありますか?
A. あります。
社協によっては、月々の返済額を減額する「少額返済制度」について相談に乗ってくれる場合があります。 [6, 10] 「全額は無理だけど、少しずつなら返せる」という場合は、返済計画の見直しが可能か問い合わせてみましょう。
困ったときの相談窓口一覧
返済に関する悩みや手続きで分からないことがあれば、一人で抱え込まずに以下の窓口に相談してください。相談は無料です。

| 相談窓口 | 相談できる内容 |
|---|---|
| お住まいの市区町村 社会福祉協議会(社協) | 返済猶予、免除、減額など、返済に関するすべての相談の基本窓口。 [10, 15] |
| 都道府県 社会福祉協議会(特例貸付事務センター) | 免除申請書の提出先。制度全般に関する問い合わせ。各都道府県にコールセンターが設置されています。 [1, 6] |
| 自立相談支援機関 | 返済問題だけでなく、家計管理、仕事探し、住まいの確保など、生活全般の困りごとを包括的に支援してくれる窓口。 [7, 11, 12, 13, 14] 各自治体に設置されています。 |
| 法テラス(日本司法支援センター) | 特例貸付以外にも借金があり返済が困難な場合に、債務整理などの法的解決について無料で相談できます。 |
まとめ:返済が苦しいときは、まず相談を
今回は、コロナ特例貸付の返済猶予や免除について解説しました。最後に、重要なポイントをまとめます。
- コロナ特例貸付の返済は2023年~2025年にかけて順次開始している。
- 返済が困難な場合、「返済免除」と「返済猶予」という2つの大きな救済措置がある。
- 返済免除は、世帯全員が住民税非課税などの条件を満たせば、申請により返済が不要になる制度。 [1]
- 返済猶予は、失業や病気などの理由で、返済を原則1年間待ってもらえる制度。 [15]
- どちらの制度も自動的には適用されず、必ず申請が必要。
- 滞納を放置すると延滞金や法的手続きのリスクがあるため、返済が苦しいと感じたらすぐに社会福祉協議会に相談することが最も重要。 [18, 22]
公的な貸付制度は、返済が困難になった人向けのセーフティネットもセットで用意されています。決して一人で悩まず、まずは勇気を出してお住まいの地域の社会福祉協議会に電話をしてみてください。きっと、あなたの状況に合った解決策を一緒に考えてくれるはずです。

